
今回は私が担当します。
私はスポーツが大好きです。若い頃から野球とかサッカーとかラグビーとか、特に球技が好きです。自らプレーをすることもありましたが、40歳を過ぎてからはもっぱら観戦です。以前は試合会場に行くこともありましたが、今は足腰が不自由でもっぱらテレビ観戦です。
まず野球ですが、プロ野球はもちろん読売ジャイアンツの大ファンです。物心ついた頃にはもうそうでした。いわば生まれながらの巨人ファンです。よく、「巨人・大鵬・卵焼き」などとからかい半分に言われますが、私は相撲は大鵬よりも柏戸、ご飯のおかずは卵焼きよりも納豆です。
巨人では、長嶋茂雄さんです。昭和33年巨人入団以来「長嶋命」と言ってもよいくらいです。この昭和33年では、長嶋選手は新人ながら開幕試合に先発出場しました。そして、当時国鉄スワローズの大エース金田正一投手に、4打席連続三振を喫しました。それも見逃しではなく、空振りの三振でした。しかしこの年は最終的に、ホームラン・打点で1位、打率は2位と大活躍しました。
巨人が勝っても、長嶋選手が打ってではないと喜びは半減以下で。長嶋選手が全得点をあげて勝つと、まさに有頂天でした。昭和40年から48年までのセリーグ・日本シリーズ9連覇は、まさに太陽が東から昇り西に沈むように、ごく当たり前の出来事でした。しかし、盛者必衰の理を現わすように、49年にはセリーグ優勝を逃し、長嶋選手の現役引退とチームの流れは退潮の時期となりました。10月に行われた引退試合の時の長嶋選手の最後の言葉、『巨人軍は永久に不滅です』は今でも悲哀と奮励の言葉として頭の奥に残っています。翌50年には長嶋監督となりますが、長嶋選手のいないチームでは如何ともしがたく最下位に沈んでしまいました。以来、一進一退を繰り返しながらファンを楽しませてくれています。
次はサッカーです。といっても日本のではなく世界のサッカーです。私がサッカーに興味を持つようになったのは、昭和39年東京、43年メキシコシティのオリンピックがきっかけでした。メキシコシティでは、日本はドイツの名将クラマー氏が監督、釜本邦茂・杉山隆一選手を中心に見事銅メダルを獲得しましたが、それよりも目に付いたのは外国チームの技術・体力の高さでした。特に素晴らしかったのは1974年(昭和49年)のワールドカップ・西ドイツ大会でした。当時日本ではサッカーはそれほど人気がなく、ワールドカップの同時中継はありませんでした。毎週確か土曜日だったと記憶していますが、ダイヤモンドサッカーという番組で週1回世界・日本のサッカーを録画で放送していました。西ドイツ大会もダイヤモンドサッカーで見るよりなかったのですが、優勝した西ドイツ、2位のオランダをはじめとする見事なプレーに目を奪われました。
ワールドカップとはいえ、現在のところ22回開催されていますが、ヨーロッパと南アメリカのチームしか優勝していません。ヨーロッパはドイツ(西ドイツ含む)・イタリアがともに4回、フランス2回、イングランド・スペインがともに1回で、計12回。南アメリカがブラジル5回、アルゼンチン3回、ウルグアイ2回で計10回。準優勝・3位も全てヨーロッパと南アメリカ勢。4位にやっと韓国とモロッコ。日本はベスト16が最高です。ヨーロッパ・南アメリカ以外のチームの奮起が期待されます。
選手は上記の西ドイツ大会などでのドイツ皇帝ベッケンバウアー、オランダのスーパースターと言われるヨハン・クライフ、ブラジルの王様ペレなど挙げればきりがありません。日本では何といっても釜本邦茂選手。私にとっては、釜本選手がこれまでで最高の選手といっても過言ではありません。今後、世界に通用する天才(=努力家)の誕生を望んで止みません。
最後にラグビーです。ラグビーは、今はありませんが松尾雄治擁する新日鉄釜石が贔屓でした。釜石出身の友達がいて、毎年1月15日の成人の日(当時)に開催される日本選手権をよく観戦に行きました。釜石の7連覇はほとんど競技場で観ました。実は、炬燵に当たりながら酒を飲んでテレビ観戦するのもいいものですが、成人の日ということで、晴れ着を召した方たち(話したことはないが)と同席の観戦もまた楽しみの一つでした。
日本ラグビーは世界的に評価が低く、ワールドカップはあまり興味がありませんでしたが、モーガン・フリーマンとマット・デイモン主演の映画『インビクタス負けざる者たち』を観て大いに惹かれました。、オールブラックス(ニュージーランド代表チームの愛称)のハカ(ウオークライ)は有名であり、日本代表チームはこの大会でオールブラックスに17-145と歴史に残る国辱的な大敗を喫したのでした。
以上、振り返ってみると私の贔屓は強いチームに偏っているようです。ですが、人間のやることですから、常勝などということはありえないのは当然です。勝った負けたを繰り返す、そして負けたからこそ切磋琢磨、猛練習により技術を高め、力を蓄えて次の雪辱を期す、これこそスポーツの醍醐味ではないでしょうか。頑張れ、日本。
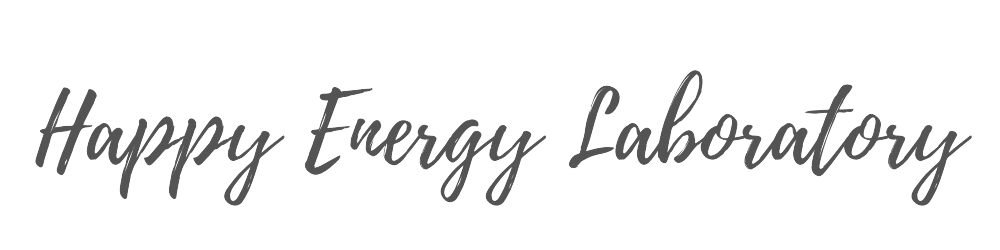
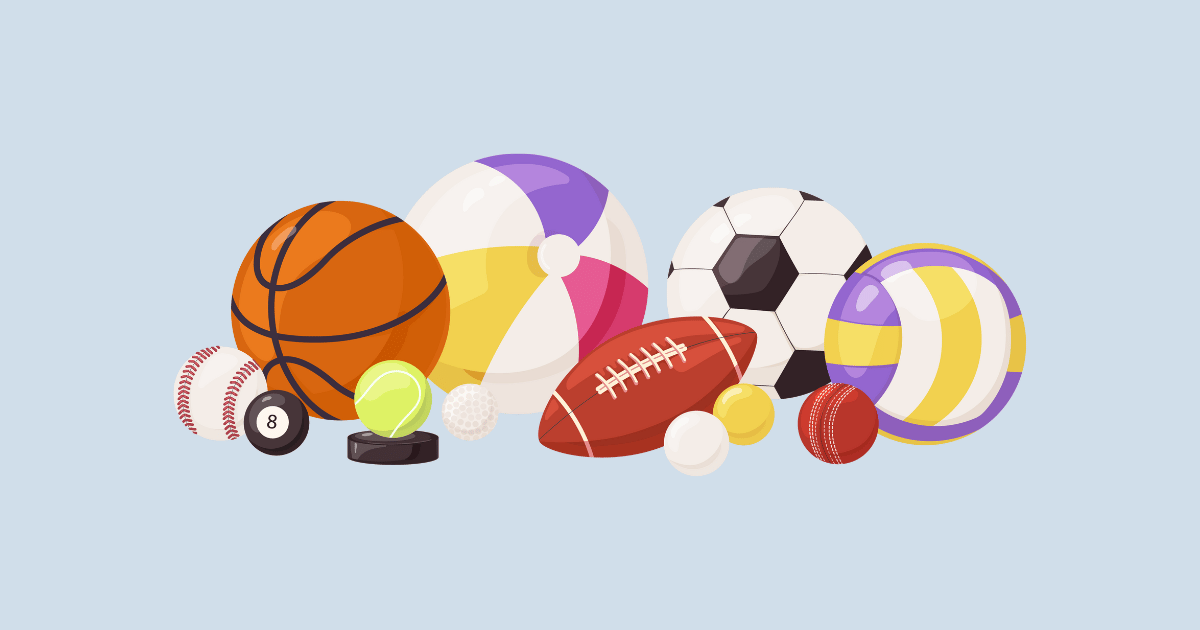


コメント