このように旧暦に興味を持ったのは、大佛次郎氏の「天皇の世紀」を読んだためである。江戸時代幕末から明治維新直後までの間を著した未完の長篇歴史小説である。当時の膨大な資料等を参照して著されたものである。明治6年に太陰太陽暦から太陽暦へ改暦されたため、そこに著されている日付等は全て旧暦によるものである。「朔」とか「望」とか「閏月」も出てくる。旧暦は月の満ち欠けにより月日を定める。一瞬でも月が全く欠ける日を「朔」=「新月」、満月の日を「望」と呼んだ。「朔」から「朔」までがひと月、それが29日か30日。そこで小の月(29日)と大の月(30日)をそれぞれ6カ月、合計で354日となり、新暦との差は年に11日。3年もするとその差はひと月になってしまう。それでは季節感がずれてしまうので、3~4年に1回「閏月」を入れて調整する。簡単に言うとこれが太陰太陽暦である。
昔は夜の照明は月の光が主である。明智光秀が6月1日から2日にかけて本能寺に織田信長を襲ったのは、闇夜にまぎれて兵を移動させ襲撃したのである。逆に、赤穂浪士が12月15日に吉良邸に討ち入りしたのは、満月の光を望んだのと、雪明かりをも望んだのではないか。間違いなく吉良上野介を討つには明るくなくてはならないからだと考える。
また旧暦には彼岸・土用などの雑節、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口などの六曜等と種々の記載がある。しかし日の吉凶によって働き方を変えるわけにはいかない現代人にとっては、星占いと同様に参考に知っておけばよいのであろう。
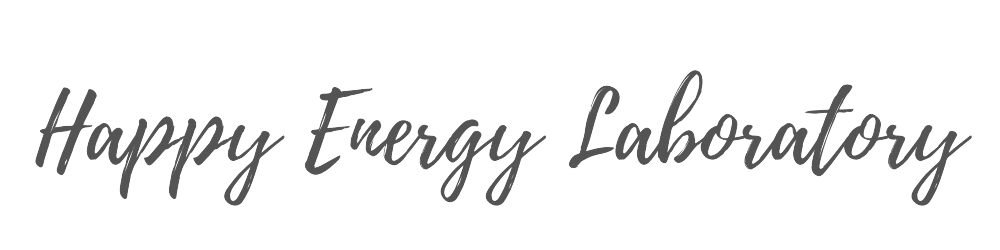
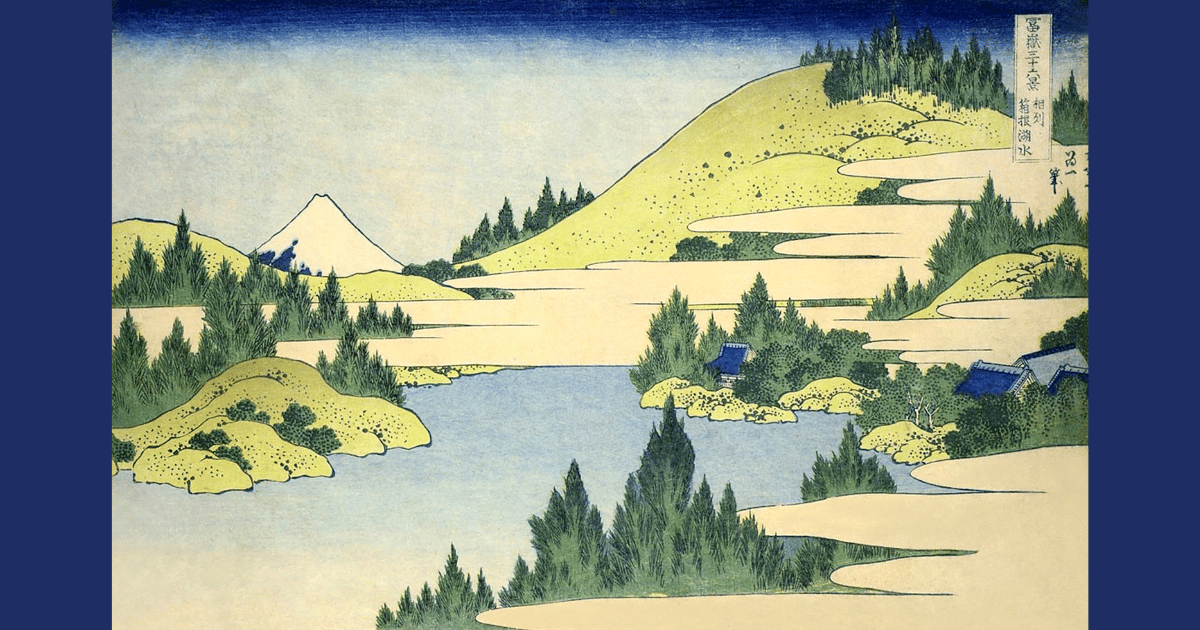


コメント