「のぼり」とは、江戸時代には、江戸から京都・上方へ行くことを「のぼる」と言った。逆は「くだる」である。今でも「くだらない」という言葉があるが、大したものでもないもの、つまらないものの意である。優れたもの、評価の高いものは、京都・上方から当時一大消費地である江戸に送られた。そうでないものは送られなかった。つまり「くだらない」のである。
「七ツ立ち」は少々ややこしい。江戸時代には時刻の表し方が複数あった。一つは子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の十二支である。「子」は現在の午後11時から午前1時の2時間、「午」は午前11時から午後1時の二時間である。この午前・午後の午は十二支の「午」である。
もう1つは数字を使うもので、午前と午後を6等分し午後の12時を九つと呼び、以下順次2時間おきに八つ・七つ・六つ・五つ・四つと呼び、午前12時からまた九・八・七・六・五・四と繰り返したのである。
「八つ」は現在でも「3時のおやつ」という言葉として残っている。昔は朝から夕まで働くというように1日2食であった。それでは途中で腹がすくため、中間の「八つ」=午後2時頃に食物を食べた。その風習が昼食を摂った後にもかかわらず残っているのである。
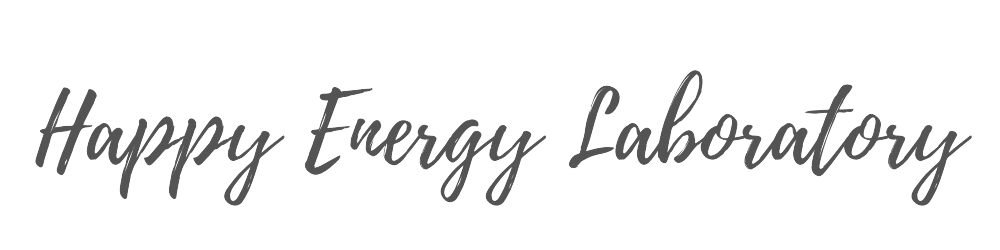
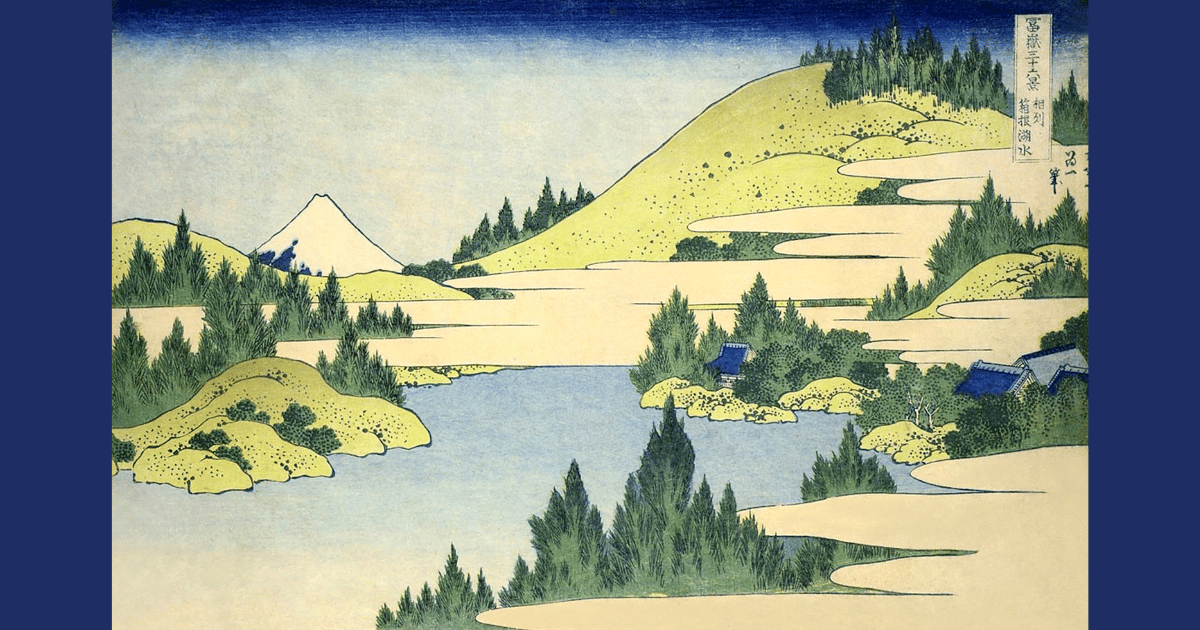


コメント